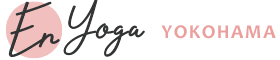ヨガ哲学初心者が圧倒的にわかりやすくなる学び方とは?
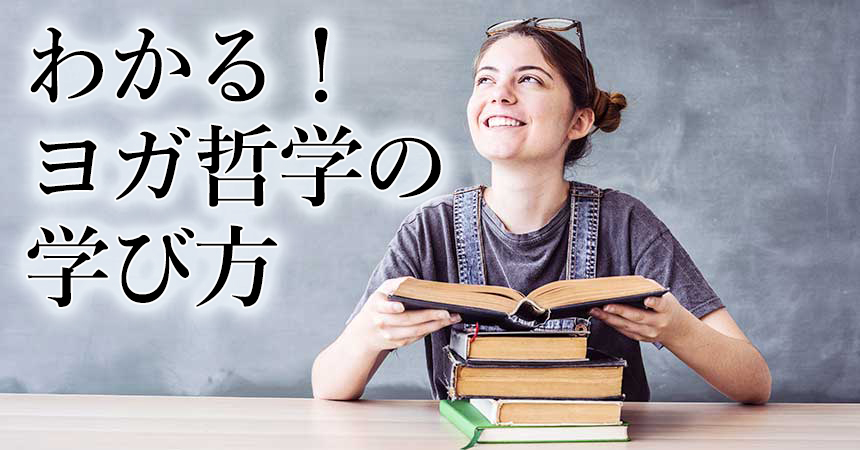
ヨガ哲学は、難しいのでしょうか?
たしかに、古代インドの哲学ですから、現代に生きる日本人の私たちにとって、とっつきにくく感じます。
しかし、学び方次第で、とてもわかりやすくなるんです。
今日は、ヨガ指導者でもある私が、試行錯誤の末につかんだ「最短でヨガ哲学が理解できる勉強方法」をお伝えします。
ヨガ哲学が難しいと思っている人、ヨガ哲学初心者さん、ヨガインストラクターを目指している人に読んでいただけると嬉しいです。
ヨガ哲学の初心者が最初に読むべきは必読書『ヨーガスートラ』
ヨガ哲学を効率よく学びたい人は、まず最初に根本教典『ヨーガスートラ』を読みます。
なぜならば、『ヨーガスートラ』は、ヨガの定義・実践方法を明快に提示した最初の教典で、ヨガ哲学の基本の1冊だからです。
『ヨーガスートラ』は日本語訳が何冊か刊行されています。
私が推奨している日本語版『ヨーガスートラ』は、「ヨーガスートラ」全文掲載のおすすめ本は、この5冊! という記事で紹介しています。
参考になさってくださいね。
なお、将来的にヨガインストラクターになりたい人や、ヨガ哲学を深く学びたい人は、『ヨーガスートラ』以外にも、読んでおくべき文献があります。
ヨガ哲学の本や参考書は、以下の順番で読むと、ヨガ哲学の全容が分かりやすいです。
- 『ヨーガ・スートラ』
サーンキヤ哲学を背景としたヨガの理論と実践としての古典ヨガを理解する。ヨガ哲学の中核をなす必読書です。 - 『ハタ・ヨーガ・プラディーピカー』
タントラの影響を受けて形成された「ハタヨーガ」の実践書。伝統的なアーサナ・プラーナーヤーマなどの具体的な技法について理解する。
※『ゲーランダ・サンヒター』と比較しながら読むのも興味深いです。 - 『バガヴァッド・ギーター』
大叙事詩『マハーバーラタ』の一部でヒンドゥー教の教典。ヨーガの定義が『ヨーガスートラ』とは異なるニュアンスであることを確認しておく。 - 『ウパニシャッド』またはインド思想に関する書籍
世界観・身体観・因果応報・輪廻・解脱などインド独特の思想について確認する。ヨガ哲学の理解を助けてくれます。
ちなみに、4つの文献は成立年代(古い)順に
『ウパニシャッド』→『ヴァガヴァッド・ギーター』→『ヨーガ・スートラ』→『ハタ・ヨーガ・プラディーピカー』となります。
ヨガ哲学の初心者は、重要単語をサンスクリット音で覚えよう

さて、『ヨーガスートラ』の本を手に入れました。
読んでみて、どうでしょう。
とっつきにくいと感じると思います。
それもそのはず、『ヨーガスートラ』は、もともとサンスクリットの詩節型式で書かれていますし、日本人にはなじみのない概念や用語が満載です。
『ヨーガスートラ』における独特な用語の日本語訳には、仏教の漢語があてがわれることもあり、意味が想像しづらく、ぼんやりとしたなんとなくの理解になりがちです。
日本語訳のみで読み進めると、意味が曖昧なままで、ヨガ哲学がより難しいものに感じられてしまいます。
まるで、登場人物が多い小説を、それぞれの人物の名前とキャラクターが一致しないまま、読み進めているようなものです。
何が起こっているのかが分からず、ワクワク感も面白さもありません。
結局はいつのまにか本を閉じるか、眠ってしまうかで、読了できません。
ですから、『ヨーガスートラ』を読み進める際は、重要単語は固有の言葉としてサンスクリット音(おん)のまま覚えるようにします。
例えば、 『ヨーガスートラ』第1章2節です。
ヨーガス チッタブルッティ ニローダハ *
*『やさしく学ぶヨガ哲学 ヨーガスートラ』
ヨーガとは心の活動を一時的に停止させることである **
**世界の名著1『バラモン教典・原始仏典』
まず、キーワードである「チッタブルッティ」は、「チッタ・ブルッティ」というサンスクリット音のまま、固有名詞として覚えます。
そして、その意味は「心の活動」と、併せて覚えます。
このように、ヨガ固有の単語は、音と意味をセットで覚え、理解します。
例えば、「コンサルティング」という外来語を、「経営上の問題解決をサポートする業務」という意味で覚え理解するのと同じ要領です。
英語学習では、単語を覚えれば覚えるほど長文読解がスムーズになりますよね。
それと同じで、ヨガ哲学の学習でも、専門用語の語彙力を高め、ボキャブラリーを増やすことで、圧倒的にストーリーが分かりやすくなるのです。
ヨガ哲学の初心者は、重要で分かりやすいスートラから読み理解しよう
『ヨーガスートラ』は全編195節で、インド哲学の教典としては短いです。
しかし、初心者にとっては情報が多いと感じることでしょう。
そこで、最初から順番に1つ1つ読み進めるのではなく、『ヨーガスートラ』のなかで重要なスートラを重点的に読むことをおすすめします。
すると、『ヨーガスートラ』のメッセージが分かりやすくなります。
前述のように、第1章2節で語られる「チッタ」「ブルッティ」「ニローダ」などは、重要な頻出単語で、ヨガの基礎用語です。
ヨガ哲学を学ぶうえで、その他にどんな用語が重要かは、以下の記事でガイドしています。参考にしてくださると、嬉しいです。
「ヨーガスートラ」重要ワードをチェック!
ヨガ哲学の初心者が『ヨーガスートラ』を最初から順番に読み進める場合、難しい、わからない、と、立ち止まってしまうスートラに必ず出会います。
わからない場合は、そこはいったん保留にして、その先を読み進めていってください。
『ヨーガスートラ』第1章そうそうでつまづいた人は、思い切って第2章から読み始めるのもおすすめです。
『ヨーガスートラ』第2章では、「クリヤー・ヨーガ(行動のヨーガ)」と「アシュターンガ・ヨーガ(ヨガ八支則)」が説かれます。
第2章部分は成立年代が古く、内容的に重要かつ、筋が通っているので頭に入りやすいです。
ヨガ哲学の初心者は『ヨーガスートラ』の本編を優先し、解説は後で読む
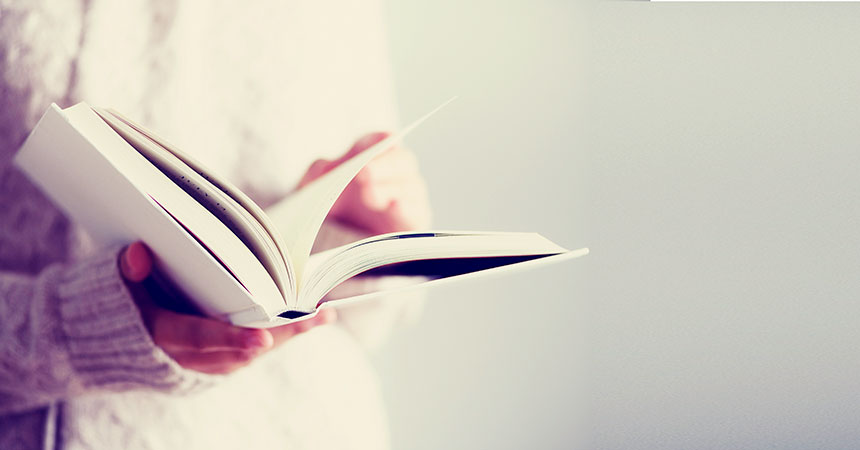
『ヨーガスートラ』の本はたいてい、パタンジャリ編纂の本編195節の日本語訳と、著者による解説という構成になっています。
ヨガ哲学をやさしくわかりやすく学びたい人は、まず「本編」を正しく読むことに集中しましょう。
ヨガ哲学の専門用語に関する語彙力を向上させ、『ヨーガスートラ』が展開する論理の整理に焦点を当てるべきです。
ただし、「解説」で補足される情報は『ヨーガスートラ』を理解する助けになります。
特に、ヴィヤーサによる註解が掲載されている場合は、読んでおくとよいでしょう。
しかし、著者の私見・持論や考察部分は、後から読むようにしましょう。
著者の思想的・実践的な立場によっては、解説で論じられる情報と本編とのつじつまが合いません。
本編と直接関係のない古今東西の事象と結びつける解説部分は、要注意です。
ヨガ哲学の初心者でも『ヨーガスートラ』がやさしく読める!
いかがでしたか?
ヨガ哲学をわかりやすくする勉強の仕方は、以下の4つです。
- ヨガ哲学は『ヨーガスートラ』から始めよう
- 重要単語はサンスクリット音のまま覚えよう
- 内容の重要度を把握し分かりやすいスートラから読んでみよう
- 本編の意味把握を重視。著者の解説は後から読もう
ヨガ哲学の初心者さんは、『ヨーガスートラ』の第2章から読み始めるといいですよ。日本人でもわかりやすく、比較的サクサク読み進められます。
最後になりますが、ヨガ哲学は、それまでなじみのなかった異文化の思想です。
少しずつ、段階的に勉強していきましょう!
ヨガ哲学が、あなたの日常に、癒しや希望をもたらしてくれますように。

わかりやすい『ヨーガスートラ』関連記事
参考文献
- 『世界の名著1バラモン教典 原始仏典』中央公論社 (1969/5/30)
- 『解説ヨーガスートラ』佐保田鶴治 著 平川出版社(1983/8/10)
- 『やさしく学ぶヨガ哲学 ヨーガスートラ』 向井田みお著 アンダーザライトヨガスクールYOGA BOOKS (2015/3/1)
【ヨガ哲学】もう忘れない!頭に染みこむ「ヨガ八支則」オンライン講座
『ヨーガスートラ』の教えの中核「ヨガ八支則」18項目を丸覚えするコツをお伝え
1.サンスクリット音のまま意味とともに暗記する(忘れない覚え方があります)
2.八支則実践のメリットや論理を整理して、はっきりと理解する
ヨガ哲学が圧倒的にわかりやすく学べる、オンライン講座のカリキュラムや受講料など詳細はこちらから。
◆ガイダンス動画限定公開中!◆