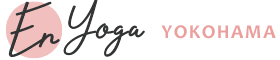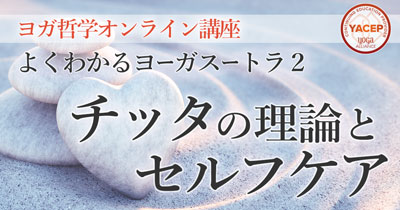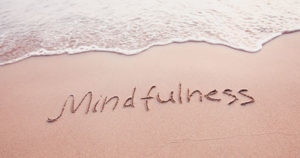今さら聞けない「マインドフルネス」と「ヨガ」の違いとは?
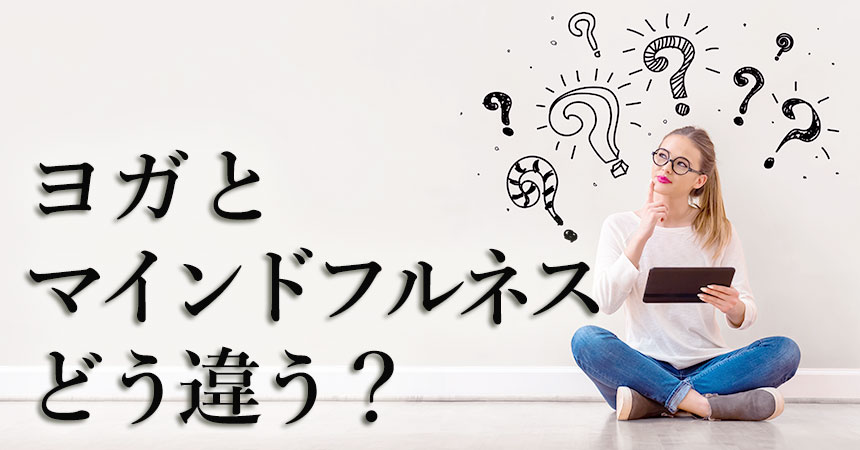
ヨガとマインドフルネスって、なんだか似ていますね。
ヨガインストラクターさんなら、生徒さんから「マインドフルネスって、何ですか?ヨガと関係ありますか?」などと質問されることがあるかもしれませんね。
ヨガとマインドフルネスには共通点があります。
それは、どちらも瞑想をする、ということです。
しかし、ヨガとマインドフルネスの違いについてはどうでしょうか。
今すぐ、すっきりと説明するのは難しいかもしれません。
そこで今日は、似て非なる「マインドフルネス」と「ヨガ」の違いや関係性を解き明かしていきましょう。
瞑想に興味がある人や、ヨガインストラクターさんにおススメの記事です。
「マインドフルネス」を有名にしたのはアメリカの心理療法

「マインドフルネス」という言葉を一躍有名にしたのは、仏教の禅に影響を受けた新しいタイプの認知行動療法「マインドフルネスストレス低減法(Mindfulness-Based Stress Reduction:MBSR)」です。
マインドフルネスストレス低減法(MBSR)とは
マインドフルネスストレス低減法(以下、MBSR)は、1980年代にアメリカのジョン・カバットジン氏が開発した、瞑想を活用した心理療法です。
目的は、医学的治療が難しい慢性的な痛みを抱える患者さんを助けることでした。
カバットジン氏は、マインドフルネスのことを「瞬間瞬間立ち現れてくる体験に対して、今の瞬間に、判断しないで、意図的に注意を払うことによって実現される気づき」としています。
MBSRのプログラムは、3種類の「マインドフルネス瞑想法」の実践・習得がメインです。
歩行瞑想やその他のワークも含め、通常は8週間かけて行われます。
結果的にMBSRは、慢性的な痛みに効果を上げ、当初の目的を果たしました。
その後、高血圧・がん・過食・パニック障害・うつ病などにも効果があること実証され、精神医学や臨床心理学の分野で注目されていきました。
MBSRのマインドフルネス瞑想法とは
MBSRで行われる「マインドフルネス瞑想法」は、注意集中力を高めるトレーニングで、仏教の瞑想がルーツです。
ここでの仏教瞑想とは、日本の大乗仏教の禅宗に伝わる瞑想だと思われます。
カバットジン氏は、著書『マインドフルネスストレス低減法』のなかで、禅宗である曹洞宗の開祖・道元の思想に影響を受けたと明かしています。
瞑想を医療分野で実践するにあたり、仏教用語や宗教的な表現は、普遍的な言葉に置き換えられました。
仏教の瞑想は、どんなバックグラウンドをもつ人でも実践できるプログラム「マインドフルネス瞑想法」へと変化したのです。
それでは、MBSRのプログラムの要である3種類の「マインドフルネス瞑想法」を紹介します。
マインドフルネスストレス低減法(MBSR)の3つのマインドフルネス瞑想法
- ボディースキャン:
仰向けでリラックスし、体の一部に注意を向ける訓練を、場所を変えながら繰り返す。 - ヨーガ瞑想法:
ヨガのアーサナのような体操を行いながら、身体感覚に注意を向ける。 - 静座瞑想法:
座って行ういわゆる瞑想。呼吸・体・音・思い・意識とともに座るなど、手順を踏んで実践する。
MBSRでは、ヨガのアーサナから着想を得たワークを「ヨーガ瞑想法」と名付けています。
実際に行っているワークは、リラックス系のヨガと非常に似ています。
しかし、ヨガ=MBSRであると、誤解してはいけません。
あくまで、MBSRは医療に近い現場で扱われるものなのです。
マインドフルネスストレス低減法(MBSR)の影響
さて、MBSRは、これまでの認知行動療法に一石を投じました。
MBSRは、効果があったのです。
患者さんの注意観察力を高め、認知の変容を促すことで、症状を改善したり再発を予防するということが確認されました。
MBSRを発展させた形で、1990年代・2000年前後には「マインドフルネス認知療法:MBCT」、「メタ認知療法:MCT」、「弁証法的行動療法:DBT)」、「アクセプタンス&コミットメントセラピー:ACT)」などが開発されました。
レーズンを食べる瞑想エクササイズは、この流れから来ています。
やがてマインドフルネスは、Googleが社員研修に取り入れたことでさらに有名に。
人材開発などの他分野へと展開され、今や「マインドフルネス」という語は、今起こっていることを注意深く観察する心の在り方として、広く浸透しているのです。
ヨガとマインドフルネスの共通点と違い
言葉のうえでのルーツ・瞑想実践のルーツとしても、ヨガはマインドフルネスに関わり合いがあります。
それゆえ、混同されやすいのが難点です。
そこで、「ヨガ」と、MBSRの「マインドフルネス瞑想法」の共通点と違いを整理してみましょう。
| 瞑想 | 対象者 | 目的 | 実践場所 | |
| ヨガ | あり | おおむね健康な人 | 解脱|健康増進 | フィットネス|ヨガスタジオ |
| マインドフルネス瞑想(MBSR) | あり | 治療が必要な人 | 治療|再発予防 | 臨床心理|医療 |
ヨガとマインドフルネス瞑想法の共通点は、瞑想と無理のない運動の実践です。
ヨガとマインドフルネス瞑想法の違いは、対象者・目的・実践場所です。
古典ヨガでの究極目的は解脱(カイヴァリヤ)でしたが、現代ヨガでは美容・心身健康増進、幸福感の向上を目的とすることが多いです。
現代ヨガの対象者は広く、実践場所もフィットネススタジオ、ヨガ専門スタジオ、公共施設など、幅が広いです。
一方で、認知療法としてのマインドフルネス瞑想の目的は、治療・再発予防・生活の質向上などです。
医療的な管理のもと、臨床心理士や特別な訓練を受けた専門家がガイドします。
まとめ:ヨガとマインドフルネスは厳密には違うので、取り扱い注意
ヨガとマインドフルネスの共通点と違いについて、述べてきました。
いかがでしたでしょうか。
最後に、ヨガ指導者の立場から、最も大きな相違点を挙げておきます。
ヨガには、ヨガ哲学、つまり実践の論理的背景となる思想があります。
その思想は、ときにインド由来の宗教色や神秘主義を帯びることがあります。
マインドフルネス瞑想法は、宗教・神秘主義とは切り離された、科学的根拠にもとづいた治療的側面のある瞑想ワークです。
この点で、ヨガインストラクターは両者を明確に区別するべきです。
ヨガにマインドフルネス瞑想法相当の効果があるとうたって、誤解を与えてはいけません。
ちなみに、言葉の定義として最も広い意味での「マインドフルネス」は、個人としての心の在り方・態度ですから、ヨガ指導の現場で活用していくことは可能です。
ただし、ヨガのレッスンで、「今この瞬間」「あるがまま」「判断しない」などマインドフルネス瞑想法由来の文言を、安易に借用しているのなら、一度は立ち止まり、考えてほしいです。
静的集中状態へ生徒さんをいざなう、ヨガ本来の作法というものがあります。
まずはヨガの技法を理解し磨いたうえで、必要に応じ、広義のマインドフルネスを発動させたいものですね。
参考文献
- 『ヨーガとサーンキヤの思想』 中村元 春秋社 (1996)
- 『マインドフルネスストレス低減法』 ジョン・カバットジン 北大路書房 (2007)
- 『 マインドフルネスとスピリチュアリティ』 井上ウィマラ 人間福祉学研究 第7巻1号 (2014)
【ヨガ哲学講座】もう迷わない! スッキリ明快「ヨーガスートラ」心のご自愛道
「チッタ」を単に「心」と理解してしまうとヨガ哲学の学びをこじらせる原因に…
スピリチュアル一切なし!文献からひも解くヨーガのココロ「チッタ」と、チッタのセルフケア方法。
ヨガ哲学が圧倒的にわかりやすく学べるオンライン講座の詳細はこちらから。
◆ガイダンス動画限定公開中!◆