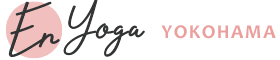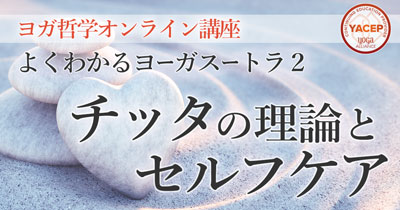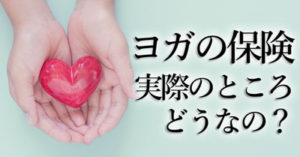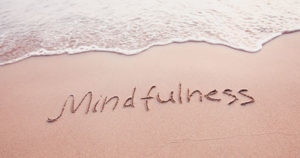ヨガとタントラの関係は?-インストラクターが知っておくべきヨガ哲学

ヨガ哲学に触れていると、ときおり「タントラ」という言葉に遭遇します。
タントラとはいったい何でしょうか。また、ヨガとはどう関係しているのでしょうか。
今日は、ヨガの側面からタントラについてわかりやすく解説します。
ヨガを深めたい人、ヨガ哲学が苦手なヨガインストラクターさんにおススメの内容です。
タントラについて知ろう!

タントラの定義を確認
タントラとは、ヒンドゥー教におけるシヴァ派のうち、シヴァ神妃シャクティを崇拝するシャクティ派の教典名です。
バラモンを階級の頂点とし、ヴェーダの権威を認めるバラモン教正統派の教典が「スートラ」であるのに対し、シャクティ派の教典が「タントラ」と名付けられたことに由来します。
後にはタントラ主義のさまざまな教典を「タントラ」と呼ぶようになりました。
タントラの思想そのものを「タントラ」として扱う場面も見受けられます。
「スートラ」も「タントラ」も、意味は同じ「縦糸」。
しかし、スートラが公(おおやけ)の教えを説くのに対し、タントラは秘密の教えを説くとされています。
タントリズムの特徴
ヒンドゥー教のタントラの教えを守るタントラ主義のことを、「タントリズム」といいます。
ちなみに、仏教におけるタントリズムのことは「密教」と呼びます。
タントリズムが起こる前のインドでは、ヴェーダを権威とするバラモン教が正統派であり思想の主流でした。
バラモン教が隠遁的で、浄・不浄の観念が強く禁欲的であるのに対し、タントリズムは、現実・世俗を重視し、操作的・神秘主義的で、生き生きとした庶民的な信仰形態をもちました。
タントリズムの特徴をまとめると、以下のとおりです。
- 世俗への考え方:現実的で、現世利益を願う
- 生や快楽:肯定的
- 儀式について:儀式、祭式、呪術を受容(土着民族思想の取り込み)
- 目的:解脱だけでなく現世での超能力も追求
- 精神と肉体:肉体も精神と同様、聖なるものとする
- 解脱への手段:男性原理と女性原理など、相反する原理の合一
ヨガの歴史とタントリズム
タントリズムの流行は、7世紀ごろです。
ヒンドゥー教シヴァ派の一派、シャクティ派の儀式では、シヴァ神とシャクティ妃の結合の象徴として、実際の男女の性的結合を用いて解脱に至ろうとしました。
このようなタントラ主義を「左道タントリズム」といいます。
一方、修行者自らの体内操作で、両神の象徴的結合を目指すタントリズムを、「右道タントリズム」といいます。
この右道タントリズムから、ハタ・ヨーガが発生していくことになります。
インド社会がタントリズム化していくなか、11世紀にはシヴァ派からナータ派が興り、13世紀ごろゴーラクシャナータが『ゴーラクシャ・シャカタン』を記しました。
ゴーラクシャナータは、ハタ・ヨーガの開祖とされます。
15世紀頃にはスヴァートラーマが『ハタ・ヨーガ・プラディーピカー』を記し、現代ヨガに連なるハタ・ヨーガが確立。
後代にはゲーランダによる『ゲーランダ・サンヒター』、シヴァ派の教典『シヴァ・サンヒター』などが記されました。
タントリズムによるヨガの変容

5世紀ごろ成立の『ヨーガ・スートラ』の修行体系が、7世紀以降流行したタントリズムに影響されて変化・発展し、10世紀以降、ハタ・ヨーガになりました。
ちなみに『ヨーガ・スートラ』が提唱する古典的なヨガは、ラージャ・ヨーガと呼ばれます。
この流れを、ごく簡素に表わすと
ラージャ・ヨーガ + タントリズム = ハタ・ヨーガ
ということになります。
ハタ・ヨーガにみられるタントリズム
ハタ・ヨーガは、ラージャ・ヨーガよりも神秘的・操作主義的な性格をもちます。
ハタ・ヨーガにおけるタントリズムの影響は、以下のようなところに表れていると考えられます。
- 浄化法、アーサナなど、肉体修練に重きを置く
- スシュムナー、クンダリニーなど、神秘的な身体観
- 男性原理と女性原理など相反する原理の結合を目指す合一思想
- バンダ、クンバカなど、身体生理操作・制御により心身を覚醒させる
- チャクラ、ムドラ―など、シンボルを活用した意識操作
「ハタ」とは、「力を加えること」「力づく」という意味です。
また、ハ=太陽、タ=月、とし、両者の合一を目指すというタントラ的な解釈もあります。
『ヨーガ・スートラ』のヨーガとハタ・ヨーガの技法の違い
ラージャ・ヨーガを行ずる『ヨーガ・スートラ』では、神様的な存在として「イーシュヴァラ」が設定されていました。
技法としては、イーシュヴァラへの祈念、イーシュヴァラの呼び名であるオームの詠唱、ヨガ八支則の実践、静的集中、瞑想の深化によって、最終的に解脱を目指しました。
一方で、ハタ・ヨーガが奉ずる神は、シヴァ神です。
ハタ・ヨーガの教典『ハタ・ヨーガ・プラディピカー』の第1章1節には、「ハタヨーガの知識を教示してくださったシヴァ神に礼拝。」と、シヴァ神を敬う表現があります。
そして、ハタ・ヨーガの技法は肉体的でダイナミックです。
頭頂に鎮座する男性原理をシヴァ神、会陰部に眠る女性原理を妃・シャクティ(クンダリニー)に見立て、ムドラ―、バンダなどさまざまな身体生理操作をもちいて象徴的な結合による心身の覚醒を起こし、解脱を目指します。
ハタ・ヨーガはラージャ・ヨーガの準備段階
ハタ・ヨーガは、ラージャ・ヨーガの準備段階とされます。
『ハタ・ヨーガ・プラディピカー』第1章1節には、「ハタ・ヨーガは、ラージャ・ヨーガに登ることを望む(人のための)はしごのようなものである。」とあります。
ラージャ・ヨーガもハタ・ヨーガの共通点は、深い瞑想状態であるサマーディ(三昧)を目標とし、輪廻からの脱却・解脱を究極の目的とするところです。
まとめ:タントラ主義の安易な取り扱いには注意!
以上、タントラとは何か、タントラとヨガの関係について、ヨガの側面からまとめてみました。
いかがでしたでしょうか?
私は、ハタ・ヨーガを源流とする現代ヨガを指導していますが、タントラ的な独特の身体観の一部には、正直なじめません。
タントリズムを無理に引用せずとも、ヨガの魅力は十分に伝わると考えます。
一方で、タントリズムの現世肯定的な姿勢は、私たちに希望や活力を与えてくれます。
タントリズムの神秘主義に癒される人がいるのもまた、事実です。
現代日本のヨガクラスで、インド思想をどのように伝えていくかは、インストラクターの裁量です。
ヨガ指導者として個性を出していく一要素になります。
ただし、ヨガ指導者養成講座で習ったタントリズムを妄信し、あたかも事実のように生徒さんに伝える行為は、控えるべきです。
ヨガ業界が信頼され発展していくために、私たちヨガインストラクターは、クラスで伝えていくべきこと、そうでもないことを慎重に見極めていきましょう。
見極める目を確かなものにするため、ヨガの歴史や思想を学び、「今、なぜヨガをするのか」、「ヨガの何が良いのか」を自分のアタマで考えて、言葉にしてください。
それが、ヨガの本質を探究することであり、あなたのヨガ哲学となるでしょう。
参考文献
- 『インドの思想』 川崎信定 放送大学教育振興会 (1993)
- 『インド人の考えたこと-インド哲学思想史講義』 宮本啓一 春秋社 (2008)
- 『ヨーガの哲学』 立川武蔵 講談社 (2013)
- 『ハタ・ヨーガ・プラディーピカー 前編』 成瀬貴良 アンダーザライト (2015)
- 『ヨーガとサーンキヤの思想』 中村元 春秋社 (1996)
- 『やさしく学ぶYOGA哲学 ハタヨーガ 基礎と実践 』 向井田みお アンダーザライト (2017)
【ヨガ哲学講座】もう迷わない! スッキリ明快「ヨーガスートラ」心のご自愛道
「チッタ」を単に「心」と理解してしまうとヨガ哲学の学びをこじらせる原因に…
スピリチュアル一切なし!文献からひも解くヨーガのココロ「チッタ」と、チッタのセルフケア方法。
ヨガ哲学が圧倒的にわかりやすく学べるオンライン講座の詳細はこちらから。
◆ガイダンス動画限定公開中!◆